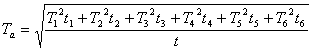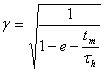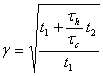| モータ | |
| 回転数 | |
|
定速回転か変速回転かを数値で明らかにする 加減速時間の長短によって、モータは一般用か制御用かに分かれる
|
|
| 慣性トルク | |
|
加減速時間中はトルクが変化する これは慣性モーメントに関係し、加減速時間が短いほどトルクは大きくなる 制御用モータ: 頻繁な始動停止や急速な動作の変化を要求されることが多く、位置決め精度などに関係するので、入念な検討が必要
|
|
| 出力 | |
|
無効エネルギを正確に計算することは難しいので、一般に効率の形で表される モータの出力は、必要動力に15~20%の余裕をみて決定する
|
|
| モータの特性曲線 | |
|
ほとんどのモータは、実用出力の範囲内でトルクが増加すると速度が下がる 速度変動率 n:全負荷速度 (min-1) この変動率の大小により、モータの特性が分かれる
|
|
| ①定速度特性(分巻特性) | |
|
トルクが変わっても速度はあまり変化しない
|
|
| ②変速度特性(直巻特性) | |
|
始動トルクが大きく、負荷が重くなると自然に速度が下がり、軽くなれば上昇する このため電源電力に変動が少ない
|
|
| 負荷の速度-トルク特性 | |
| ①定トルク負荷 | |
|
定トルク特性は速度が変わってもトルクに変化がない
|
|
| ②てい減トルク負荷 | |
|
負荷トルクの増加と共にモータの回転速度も増加する 回転速度が増すにつれて負荷トルクも増加するファンやブロア、ポンプなどの流体機械に適する 負荷トルクは速度の2乗に比例するので、2乗トルク負荷と呼ぶことがある
|
|
| ③変動トルク負荷 | |
|
使用状況により負荷が変動する その時モータの速度も変動するようでは困るので、定速度特性のモータを選ぶ
|
|
| 安定運転の判別 | |
|
運転が安定であるかどうかは、モータのトルクTMと負荷トルクTLを1つのグラフに表して判別する
後日
|
|
| DCとACによるモータの違い | |
| DCモータの利点と欠点 | |
|
1.速度制御が容易 近年の半導体技術の発達により、DCモータの最大の欠点の原因になっていたブラシがないブラシレスモータが開発された.このためDCモータとACモータの使い分けは、特性上の違いや変速の容易さなどだけである
|
|
| 速度制御 | |
|
制御用モータ 自動制御 位置決め制御 始動停止時には負荷の慣性力により、どんな場合でもトルクと速度が変化することを忘れてはならない
|
|
| モータの選定の手順 | |
|
以下の項目は最低限明確にしておく 1.定格出力
|
|
| 手順 | |
|
①設計仕様 ⑤定速回転駆動、可変速回転駆動の区別 ⑪電源の種類 ⑯環境条件
|
|
| 動力供給用の選び方 | |
| E種モータ(汎用モータ) | |
|
一般的に汎用モータは最も広く用いられている三相かご形モータを意味する場合が多い JIS C 4210,4211では、誘導モータの特性と絶縁(E種絶縁)を規定し、どのメーカのモータを使用してもほぼ同じ特性が得られるようにしている。
|
|
| モータ選定の注意点 | |
| 定速駆動 | |
|
1.モータ仕様の始動トルクと温度上昇
|
|
| 可変速駆動 | |
|
1.総合効率(制御器などの負荷装置を用いた場合は、
|
|
| 始動トルク | |||||||||||
|
制御用モータの選定では始動トルクを計算してそれに見合ったモータを選ぶ 回転速度がゼロの値を読取り、始動時にどの程度のトルクが許容できるかを知ることができる
|
|
||||||||||
| 絶縁の種類 | |||||||||||
|
絶縁材料は10年、20年という長い年月の使用に十分耐えられるように設計されている しかし、使用温度が高いと寿命が短くなると言われている
|
電気機器の絶縁物と許容最高温度 | ||||||||||
|
絶縁物の種類 |
最高許容温度℃ |
||||||||||
|
A種絶縁 |
105 |
||||||||||
|
E種絶縁 |
120 |
||||||||||
|
B種絶縁 |
130 |
||||||||||
|
F種絶縁 |
155 |
||||||||||
|
H種絶縁 |
180 |
||||||||||
| モータの温度上昇限界 | |||||||||||
|
モータの部分 |
温度(℃) |
||||||||||
|
A種 |
E種 |
B種 |
F種 |
H種 |
|||||||
|
交流機固定子巻線 整流子を持つ電機子巻線 絶縁された回転子巻線 |
50* |
65* |
70* |
85* |
105* |
||||||
|
鉄心その他の機械的部分で絶縁した巻線と近接した部分 |
60 |
75 |
80 |
100 |
125 |
||||||
|
鉄心その他の機械的部分で絶縁した巻線に近接しない部分 ブラシおよびブラシ保持器 |
機械的に支障なく、かつ付近の絶縁物に 支障を起こさない温度 |
||||||||||
|
整流子およびスリップリング |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
||||||
|
*全閉形に対しては*印の付してある上表の値よりも5℃高く温度上昇限度を定める。(周囲温度40℃) |
|||||||||||
| 定格の使い分け | ||
|
モータは常温においても、印加電圧が許容耐圧限度を超えると絶縁破壊を起こす
|
|
|
| 等価連続トルク | ||
|
負荷トルクが変動する場合は、各トルクの2乗平均を求める
|
|
|
| 出力倍率 | ||
|
連続定格で設計された装置を短時間tm分だけ運転する場合は、連続定格出力以上で使用できる tm:運転時間
|
τh:温度上昇時における熱時定数 (min) |
|
|
モータの種類 |
τh(分)の値 |
|
|
開放形 |
20~30 |
|
|
全閉外扇形 |
40~80 |
|
|
全閉自冷形 |
80~120 |
|
|
|
||
| 連続定格のものを反復使用で用いるとき | ||
|
t1:負荷時間 ドイツ電気技術協会のVDEでは、反復使用においてはt1/(t1+t2)を負荷時間率といい百分率で表し、%EDと呼ぶ
|
|
|