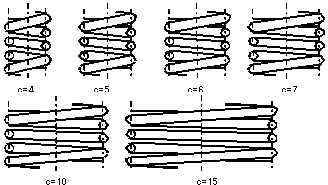| ばね寸法の決定方法 | |||||||
| 設計条件やばねを取り付ける部分の計画図から好適範囲を決めます | |||||||
| ①材料直径 | |||||||
|
計画図より、d=** 以下 |
ばね材料の引張強さ |
||||||
| (N/mm2) | |||||||
|
材料直径[mm] |
SWB |
SWC |
SWPA |
SWPB |
SWPV |
||
| 2 |
1471 |
1716 |
1814 |
2010 |
1765 |
||
| 2.3 |
1422 |
1667 |
1765 |
1961 |
1716 |
||
| 2.6 |
1422 |
1667 |
1765 |
1961 |
1716 |
||
|
2.9 |
- |
1618 |
1716 |
1912 |
1716 |
||
|
3.2 |
1373 |
1569 |
1667 |
1863 |
1667 |
||
|
3.5 |
- |
1569 |
1667 |
1814 |
1667 |
||
|
4 |
1373 |
1569 |
1667 |
1814 |
1667 |
||
|
4.5 |
1324 |
1520 |
1618 |
1765 |
1618 |
||
|
5 |
1324 |
1520 |
1618 |
1765 |
1618 |
||
|
5.5 |
1375 |
1471 |
1569 |
1715 |
1569 |
||
|
6 |
1226 |
1422 |
1520 |
1667 |
1520 |
||
|
6.5 |
1226 |
1422 |
1520 |
- |
- |
||
| ②ばね指数 | |||||||
|
JIS2704より,C=4~22 (右図より,感覚でさらに絞る) |
ばね指数の変化によるばねの形状 | ||||||
|
|
|||||||
| ③ばね定数 | |||||||
|
計画図のP-δ図表より
=**~** [kgf/mm]
中間値 = = ** [kgf/mm] |
|
||||||
| ④有効巻数 | |||||||
|
材料を鋼材とすれば、G=8000 kgf/mm2 ばね定数の式で、d4,D3をばね指数cで表せば、
または、
圧縮コイルばねでは両端の座巻を同じにし、巻き始めと巻き終わりが180°の位置にあると据わりが良い。そこで有効巻数は0.50端数がつくのが良い |
計画図よりD=25 [mm] , k=1.67 [kgf/mm](中間値),c=6 とすれば、
Na=11.5
c=D/dより、 d=4.17 → 材料表より、d=4または4.5 |
||||||
| ばね材 | |||
|
ばね材としてよく使用されるのに、ピアノ線、硬鋼線、ステンレスなどがある。 ばね鋼:焼入れ焼戻しをすると、引張強さや疲労限界も大きく なる特徴を持つ ピアノ線: 寸法精度、機械的性質、表面品位、耐疲労性などが 優れており信頼性が高い材料 SWP-A 耐疲労性を重視する動的高応力ばねに用いる SWP-B 静的高応力ばねに用いる ピアノ線と硬鋼線: 錆びやすいという特徴があるので、防錆剤添付もしく は表面処理(メッキ処理等)を行う 同寸法で製作された場合、同じ強さのばねになるが、 引張り強さの違いから耐へたり性、耐久性でピアノ線 の方が優れている ステンレス線などに比べ安価ですが表面処理をすると ト-タルでは高価になることもある。 オイルテンパ線: 硬鋼線やピアノ線に比べて比抗張力と耐熱性に優れ ている 加工性は劣るので、D/dが4未満の小さいばねには 不向き 水素脆性防止のため、メッキや酸洗いは避ける ステンレス鋼線: 耐食性、耐熱性に優れる 最も汎用性が高い鋼種はSUS304WP-B(硬質仕上げ) 伸線加工によって高強度化すると弱磁性になる 錆びにくいと同時に高温での強度(300゜強)が大きい ところから急速に普及してきたばね材。 銅合金線: りん青銅線が一般的 電気伝導性、非磁性、耐食性、加工性に優れる ばねの設計の際に必要な横弾性係数Gという値がある。このGというのは、材料固有の値(同じ値もあり)でこのGの値の違いから全く同寸法ばねでも強さ(荷重)が異なるということがわかる。 |
ばねの材料とGの値 |
||
|
(kgf/mm2) |
|||
|
硬鋼線 |
SWC |
8000 |
|
|
ステンレス線 |
SUS |
7000 |
|
|
黄銅線 |
BSW |
4000 |
|
|
ピアノ線 |
SWP |
8000 |
|
|
リン青銅線 |
PBW |
4500 |
|
|
ベリリウム銅線 |
BeCW |
5000 |
|
|
|
|||
| 要目表 | |||
|
項目 |
指定 |
単位 |
|
|
材料 |
SUP6 |
- |
|
|
材料直径 |
18 |
mm |
|
|
コイル平均径 |
100 |
mm |
|
|
総巻数 |
10 |
- |
|
|
座巻数 |
両端各1 |
- |
|
|
巻き向 |
右 |
- |
|
|
自由高さ |
約310 |
mm |
|
|
ばね特性の 指定 |
指定荷重 |
800 |
kgf |
|
指定荷重時の高さ |
250±3.5 |
mm |
|
|
指定荷重点 |
550,1100 |
kgf |
|
|
指定荷重点におけるばね定数 |
13.1±10% |
kgf/mm |
|
|
指定荷重(高さ)時の応力 |
35 |
kgf/mm2 |
|
|
試験荷重 |
1700 |
kgf |
|
|
試験荷重時の応力 |
75 |
Kgf/mm2 |
|
|
密着高さ |
180以下 |
mm |
|
|
コイル端部の形状 |
クローズドエンド |
- |
|
|
表面処理 |
材料の表面加工 |
研削 |
- |
|
成形後の表面加工 |
ショットピーニング |
- |
|
|
さび止め処理 |
黒染 |
- |
|
| 圧縮ばね 巻き数: 有効巻き数は3巻き以上で設計する 3巻き以下の場合は、理論値とごさが生じ易くなりばね定数が変動する 1.5巻き以下形状的に不安定で製作が困難になり、荷重の偏心が生じ局部応力集中による 早期損傷につながる 端部の形状: 座巻きは一般的にクローズエンド一巻き設計する 3/4巻きや1/2巻きは製作上一定形状にし難く、特性が不安定になる 一般に線径0.5mm以下では研削しない 巻き方向: ばね製作上右巻きが一般的 図面に指示がない場合は右巻きで製作される 組み合わせばねは、どちらかを反対方向に指定することで荷重が安定する 傾き(直角度): 傾きは一般的に3°以下 ピッチの粗いばねや縦横比(自由高さ/コイル平均径)が4以上のばねは、3°以下には 製作困難有効巻き数が**.5巻きのような半巻きの方が、直角度を安定させやすくなる ピッチ: ピッチはコイル平均径/2以下、ピッチ角は10°以下を目標とする ピッチが大きくなるにつれ、設計荷重との食い違い、荷重の偏心、圧縮した時に中央が膨らむ (胴曲がり)などの問題が生じやすくなる ばね指数: コイル平均径/線径は、製作上4~30程度まで可能であるが、品質安定の点から考えて 8~14の範囲に設計する 縦横比: 自由高さ/コイル平均径が大きくなるにつれ、座屈が生じやすくなるため、一般に4以下で 設計する 設計上、自由高さ/コイル平均径が大きくなる場合は、機構上で内径に案内棒を 設けるか、 外径側にガイドを用いた構造にする |
| 引張りばね 初張力: 一般的にばね指数が大きくなるほど初張力は小さくなるが、ゼロに近いばねの 製作は極めて困難である 巻き数の指定: 巻き数が10巻きより多い場合は、線径許容差により自由長さに誤差が生じる フックの形状: フック径を胴体部のコイル径より大きくすると、フックに塑性変形が生じやすくなる ため、フック径と胴体部のコイル径は同一に設計する 伸び代: 引張りばねの伸びの範囲は、自由長さの2倍までが一般的 |
| ねじりばね 巻き数: 設計荷重と実際の荷重の違いを小さくするため、3巻き以上 トルク負荷方向: 巻き込む方向に負荷が加わるように使用 どうしても巻き戻し方向に使う場合は、曲げ応力修正係数を考慮した強度計算が必要 内径の変化: ばねの内径側にシャフトを使用する場合、シャフト径は (D-ΔD)×0.9以下 ΔD=(Δn/n)×D D:無負荷のコイル中心径 ΔD:トルクが負荷された時のコイル中心径の減少量 n:無負荷時の有効巻き数 Δn:トルクが負荷された時の巻き数の増加量 端部の形状: 端末の腕を曲げる場合は、できるだけ大きな内R形状(素材径の2倍以上)にする |