荷重条件
グループ溶接継手
すみ肉溶接継手
止端の母材
引張力または圧縮力Pを受ける場合
![]()
![]()
![]()
せん断力Qを受ける場合
![]()
![]()
![]()
曲げモーメントをうける場合
![]() または
または![]()
![]()
![]()
曲げモーメントMおよびせん断力Qを同時に受け、その組合せを考慮する場合
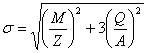
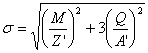
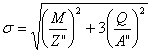
σ、τ:継手に生じる応力
A:のど断面積
a:角すみ肉ののど厚=0.7×すみ肉のサイズ
l:角すみ肉溶接の有効長さ
I:のど断面の断面二次モーメント
y:中立軸からの距離
Z:のど断面の断面係数
Z’:各すみ肉ののど断面を母体断面と平行な面に転写して得られる図形の断面係数
Z”:止端の母材断面の断面係数
A’:せん断力を負担するすみ肉の有効のど断面積
A”止端の母材断面積