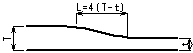| 鋳造 |
| 模型の勾配 |
|
一般的に抜け勾配は、見切り面に直角な鋳物表面で2度から3度程度
|
|
| 機械加工の削り代 |
|
通常の加工の削り代は、最も小さい鋳物でも少なくても2〜3mmとするのが至当
|
|
| 鋳鉄の機械的性質 |
|
ブリネル硬さを規定する場合に、設計者と鋳造者の双方はブリネル固さが絶対的な再現性を持つものではないこと、特に標準10mm径でない小さい鋼球を鋳鉄に使用する場合、測定値が変動するという事実を容認し、考慮に入れなくてはならない。
|
|
| 鋳物肉厚の変動 |
|
設計の原則
・指向性凝固が得られるような形状の設計
・押湯を近づけることができぬ厚肉部をなくした設計
・可能な限り均一な断面寸法にした設計
|
|
| 過熱部(ホットスポット)の影響 |
|
過熱部形成を防止する原則
・鋭角部や断面の急激なる変化を避ける
・砂型の薄肉になったところ、角ばったところで欲湯のいくつかの壁面に囲まれる形状を避ける
|
|
| 断面肉厚の変化 |
|
L=4(T−t)
|
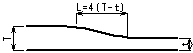
|
| 丸みアールの必要性 |
|
アールをつけることの目的
・結晶粒子の方向性が好ましい姿となり応力集中を緩和する
・熱間き裂や引け巣発生の危険を減少する
・鋳型面でも隅部の造型性を良くし、砂かみの発生を減少する
過大なアール
アールを全くつけないことと同じ位、アールを過大にすることも有害
過大なアールは鋳鉄の引張り強さを減少し、更には引け巣発生の危険を増す
接合部における面取りの半径R
R=T/3〜T/2
|
|
| 補強リブの設計 |
|
リブの厚みは、リブが取付く鋳物部分の厚みの約80%であること
リブの高さは、リブの厚みの4倍ないし6倍までであること
リブの造型は難しいので、リブには十分なテーパ−をつけること
リブの頂部は、き裂のの危険を避けるため丸くすること
模型の方案を工夫し、リブの頂部に2つの中子の合せ面による鋳張りが生じないようにすること.この鋳張りが発生する場合はリブの頂部にき裂の起こる危険が非常に大となる
リブを互い違いに付して、肉厚断面が寄り集まるのを避ける
|
|
| 角ばった構造と丸みをおびた構造 |
|
鋳造された金属の大部分は切欠きに敏感であり、更に凝固時の結晶の方向性は、鋳放しで形成される鋭角部に脆弱な面を作りだすような方向に常になっている
基本原則
形状を角張った正方形とか長方形でなく円形や長円形にするように努める
この注意は、鋳物の壁にかなりの穴をあける時にも適用すべき
|
|
| 中子による穴あけ |
|
肉の厚い断面部の内部に細くて長い中子を入れて、鋳放しであけることを計画してはならない
原則
中子を包む鋳物の肉厚より中子の直径が小さくなる時は中子を入れるべきではない.これより小さい穴が必要な場合には、特別な手段(第6章)をとるか、ドリルで穴をあける
|
|
| 過大に厚い部分 |
|
各等級の鋳鉄は、鋳造できる最小肉厚があるのと同様に、それ以上の肉厚では機械的強さの減少が大きくて使い物にならなくなる最大肉厚もある
過大な肉厚は収縮による引け巣を大きくするから、それを防ぐのに押湯や冷金が必要になり、その分生産原価の上昇を招くことになる
|
図 引張強さに及ぼす断面肉厚の影響
|
| 鋳造品設計上の一般原則 |
|
原則1.
最終図面を配布する前に有能な鋳造工場又は木型工場の人達と協議する
|
|
|
原則2.
小さいモデルを作る.又は鋳造品の形を認識しやすい図を作る
|
|
|
原則3.
鋳造品の健全性を得る為の設計をする
|
|
|
原則4.
常に冷却面を用意し、そして鋭角になる部分を避ける
|
|
|
原則5.
接合する断面の数を少なくする
|
|
|
原則6.
すべての断面部分の厚みを可能な限り均一にする
|
|
|
原則7.
内部の壁の厚みを正しく均整のとれた寸法とする
|
通例として内部の壁の厚みは外部の肉厚の9/10とするのが適切
シリンダーとブッシュ
シリンダーやブッシュ類の内径は鋳造品の肉厚よりも大きいことを原則とする
シリンダーの内径が鋳造品の肉厚よりも小さいときは、むしろ中子をなしにしてむくに鋳造する方が良い.この方が穴を安価にあけることができるし、失敗もない.
|
|
原則8.
急激な断面形状の変化を避ける.断面接合部での鋭い隅部をなくする.
|
断面接合部での2つの肉厚の相対的な違いは出来る限り小さくし、その比率で2対1を越してはならない
大きな差がどうしても避けられぬ時は、2つの鋳造品に分離することを考えてみるべき
肉厚の相違が2対1よりも小さいときは、接合部に丸みをつけるだけでよいが、それよりも大きい時は、楔状に勾配をつけて接合部を作るのが望ましい
この勾配を付した肉厚変動部の勾配は1:4以下でなくてはならない
|
|
原則9.
鋭角部にはすべて丸みをつける
|
利点:
1.鋳造品使用時の応力集中度を減少する
2.凹部になっている隅部の冷間、熱間の亀裂や外引けを防ぐ
3.隅部の造型を容易にし、過熱部の生成をなくする
1つの木型における面取り半径の種類は少ないほど良く、できれば一つだけにしたい
過大な面取り半径は好ましくなく、半径は接合部肉厚の1/2以下であるようにしたい
V字形とかY字形の断面接合部とか、他の角張った形状の個所は、局部的な過熱を避けるために丸みが豊富にある設計にしなくてはならない
|
|
原則10.
最大の効果のあるリブやブラケットを設計する
|
リブの作用
1.鋳造品の堅牢性を向上する
2.鋳造品の重量を減少する
リブに関する普通の設計で好ましいのは、厚みよりも深さを大きくすること
リブに圧縮応力がかかっているとき、引張り応力のかかる時よりも安全係数は高くなる
直交するリブや鋳造品壁の両側につくリブは避けなくてはならない
鋳物本体との接続部を可能な限り長くしてはいけない
ブラケットを別に鋳込んで、あとで本体に取付けることもしばしば行われている
これにより造型が簡易となり、原価節減が得られる
熱の集中をリブ又はウェブにあけた中子による穴で防ぐのがよい
この穴は強さ、剛性が許す限り大きい方が良い
|
|
原則11.
絶対に必要でない限り、ボス、突起部、パッドを鋳造品につけてはならない
|
取り付けボルトその他のために当り面をミリング加工とか皿穴座ぐりで作る場合は、鋳造品の設計の中にボス部を含ませない方がよい
|
|
ボスやパッドの厚み
それが取り付く鋳造品壁の厚みより少ないほうが望ましい
|
|
| この原則を適用できない場合の最小高さの推奨値 |
| 鋳造品の長さの概数 |
ボスの高さ
|
|
フィート
|
mm
|
インチ
|
mm
|
|
1・1/2まで
|
457.2
|
1/4
|
6.35
|
|
1・1/2から6まで
|
457.2〜1828.8
|
3/4
|
19.05
|
|
6以上
|
1828.8
|
1.0
|
25.4
|